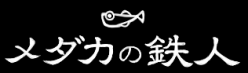【めだかの種類①】
クリックできる目次
めだかとは
「めだか」とは、ダツ目メダカ科メダカ属に分類される淡水魚の総称をいいます。
「きたのめだか」と「みなみめだか」の事を「日本めだか」というそうですが、昔は同じ種類だとされていた2種は最近になって別の品種だと判明し分離したそうです。現在は環境省により絶滅危惧種に指定されています。
私たちのよく見る野生の「めだか」は「黒めだか」といいます。童謡の「めだかの学校」に出てくる「めだか」はこの「めだか」の事です。「黒めだか」とはいいつつも、色は黒ではなく、茶色や灰色だったりします。黒めだかは、原種に近い「めだか」の品種です。
「めだか」の種類名は正式には決まっていないようです。
本やサイト、ショップによって名前に違いがありました。
色や形に特徴がある品種によって、その特徴を生かした通称で呼ばれています。
そういった「黒めだか」とは異なる色や形をした「めだか」は、ブリーダーさんの探求心と、努力と、愛で誕生しています。
新種のめだか
新種の「めだか」を誕生させるには、2種類の方法があります。
突然変異で生まれた「めだか」と、健全な「めだか」を交配して変異した遺伝子を子供に残す方法、そして、異なる種類のめだかを交配し、あらたな遺伝子を作る方法です。
ほとんどの突然変異の「めだか」は、子供に親の特徴は現れないそうです。突然変異の特徴が出やすいのは孫の世代に当たる「めだか」なのだそうです。
「めだか」には3つの色素があり、その中の、黒色素胞、白色素胞、黄色素胞を持っているかいないかで色が決まります。黄色が強く出ると、朱色の「めだか」になったり、白色の色素をのみを持って生まれた「めだか」は白くなります。逆に黒色の色素のみを持って生まれた「めだか」は黒い「めだか」になります。
メラニン色素を持たない「アルビノめだか」もいるそうです。「アルビノめだか」は目にも色素がないので、血管が透き通ることにより赤い目に見えるのだそう。
ではいろんなめだかを…
ではどのような種類のめだかがいるのでしょうか。
いくつか私の気になっている「めだか」を紹介します。
①黄めだか
黒メダカから突然変異して生まれた黄色い「めだか」です。
黒色の遺伝子持たず、黄色の色素が強く出ており、体が黄身を帯びています。
昔から親しまれてる種類だそうです。
②黄金めだか
一見「茶色めだか」のように見えますが、暗めの容器に入れると黄金色が際立って見えるそうです。
ラメが入った「黄金めだか」は金色が映えてますますきれいに見えます。
③錦めだか
その名の通り錦鯉のように、白、赤、黒をちりばめた色の「めだか」は「ミニチュアの鯉」と言われているそうです。
「三色めだか」や「三色錦めだか」とも呼ばれています。希少価値の高い「めだか」です。
水槽の中を泳ぐミニチュアの錦鯉…想像するだけで可愛いこと間違いなしです。
④スモールアイめだか
この「めだか」、目が小さく視力はほとんどありません。
そのため、えさを食べるのが下手なので、ほかの種類の「めだか」と同じ水槽で飼育はできません。
黒目の部分が萎縮して視力が弱いので、体色の変化が少ないのが特徴の「めだか」です。
「スモールアイめだか」は別名、「点目めだか」や「男前めだか」と呼ばれているそうです。確かに、見ていただければわかる通り、男前です。
⑤螺鈿光めだか
背中の光が斑紋に入る「めだか」を「螺鈿光めだか」といいます。
メスばかり生まれやすく、オスが生まれるのは10%以下とオスの「螺鈿光めだか」は希少価値が高いそうです。
白系統と青系統が生まれるそうですが、「螺鈿光めだか」に分類されるのは白系統のみなのだそう。
螺鈿細工のように見えることから「螺鈿光めだか」と命名されたそうです。
ちなみに螺鈿細工とは、貝片を木地や漆面に装着して施す装飾法です。
いかがでしたでしょうか?
「めだか」の種類は現在600種類を超えるとも言われているので、ここで紹介した「めだか」はきっと、「めだか」界隈では有名な「めだか」ばかりだと思います。
それでもこれだけ魅力的な「めだか」ばかりなのだから、「めだか」の世界は奥が深いです。