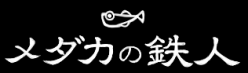【小川や田んぼにいる小さな魚といえば…】
クリックできる目次
漢字の問題
突然ですが、漢字の読み問題です。
この漢字はなんと読むのでしょうか?
①目高
②麦魚
③撮千魚
④丁斑魚
⑤鱂
ヒント1「みんな魚の名前」
ほとんどの問題に魚の文字が入っているのでなんとなく予想がつきますね。
ヒント2「みんな小さな魚」
なんとなく分かる人が出てくるかも知れません…。
ヒント3「みんな童謡に登場する」
これできっと分かっちゃいますよね?
はい、時間切れです。
…どうですか?分かりましたか?
…正解は「めだか」です。
ちょっとずるいかもしれませんが、①から⑤まですべて「めだか」と読みます。
①はそのまま読めば良いのでとても分かりやすいです。
目が大きくて、体の先の高い位置に目があるように見えることから「めだか」と呼ばれるようになったようです。ですので、目が高いで「めだか」は大変分かりやすい漢字の名前です。
その他の漢字の充て方にも意味があると思うので気になった方は調べてみてください。
また、上記の他にも「めだか」と読む漢字があるかもしれないので(間違いなくあると思います)、そちらも気になった方は調べてみてください。
より「めだか」に興味が湧くかもしれません。
めだかの名前
「めだか」は日本国内でも様々な名前で呼ばれていました。
「めだかっこ」や「めざか」であれば、なんとなくどこかで聞いた事のあるようなニュアンスで端々に「めだか」感が漂っていますが、地方によっては別の魚の名前や「うあいご」「めめんじゃこ」等、何の名前なのかわからないものまでありました。
そんな「めだか」、当たり前ですがどこでも「めだか」と呼ばれているわけではありません。
英語では「Japanese Medaka」や「Japanese rice fish」や「Jpanese killifish」と表現するそうです。
rice=米、killi=小川や水路ということで、前出の漢字でも「麦魚」で「めだか」と読むということですから、水田やそのそばの小川などで見かけることが関係しているのかもしれません。ちなみに、killifishは色々な卵を産む小さな種類の魚に使われる英語だそうですよ。
「めだか」の種類によっても違うのですが、「みなみめだか」の学名は「Oryzias latipes」というそうです。学名はラテン語だそうで、さっぱりわからず調べてみたところ、最初の部分の「Oryzias」はギリシャ語の「米」や「稲」という「Oryza」という言葉からからきていて、後半の 「latipes」は「広い足(ヒレ)」という意味でした。 そのまま訳すと「足(ヒレ)の広い稲の周りにいる者」という意味なのだそうです。またしても米関連。
その「みなみめだか」という「めだか」を確認してみましたが個人的見解としては、特に広い足(ヒレ)とは感じませんでした。すみません。「めだか」が好きな方からしたらもしかしたら大きめの尾ヒレなのかもしれませんね。すみません。
同種とされていて、そののち別種と判明した「きたのめだか」は「Oryzias sakaizumii」というそうです。最初の部分は「みなみめだか」と同じですが、後半は「さかいずみ」と読めますね。これはメダカの研究に貢献した酒泉満さんという方のお名前からつけられたのだそうです。
「めだか」は、食べると目(芽)が出ると言われたり、目が良くなるなどと言われていたそうです。名前にちなんででしょうか。そもそも「めだか」は食べるというより飼育する感覚でいたので、食べることに驚きました。
小さいし、たくさん食べないと食べた気がしないと思います。どんな味がするのかも気になりますね。
懐かしさを感じる生き物
「めだか」という子どもの頃からなんとなく触れてきている魚を調べるだけでも、こんなにも色々と知らないことがあるのだと身近にあった謎に楽しい気持ちになりました。
そんな「めだか」は現在絶滅危惧種に指定されているそうです。
昔は田んぼや小川に当たり前のようにいた魚が数が減っていなくなってしまう可能性があるとはついぞ知りませんでした。
皆様も身近にある、当たり前のものについて調べてみてはいかがでしょうか。